Japanese translation of Stephen Cooper, Augustine for Armchair Theologians (Louisville: Westminster John Knox, 2002); Tokyo: Kyobunkwan, 2012.
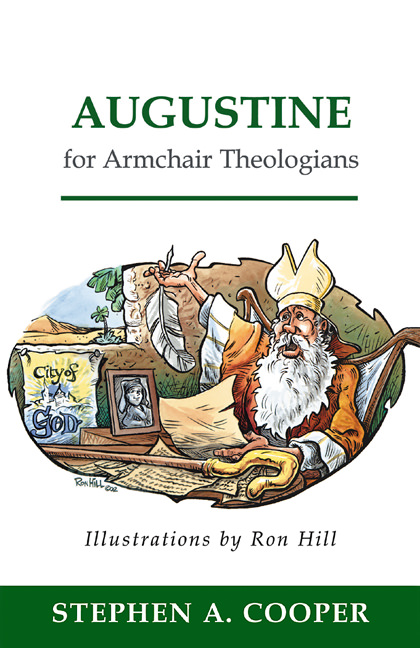 From the back cover: ‘In this book, Stephen Cooper provides an overview of one of the greatest theologians of the early church: Augustine of Hippo. Through discussing the Confessions, Cooper introduces the life and thought of Augustine and examines his theological views that emerged through the important controversies of his time.’
Again from the back cover: ‘Stephen Cooper deftly takes us into Augustine’s complex ancient thought-world and surprises us with the discovery that his seemingly distant and foreign questions are still our own. With original and lively translations of the Confessions, we are made to feel the passion and provocation of Augustine’s own Latin prose. This is an integral work that conceals between the lines a wealth of contemporary scholarship on this pioneering Western theologian and the sweep of his spiritual vision.’ by Thomas F. Martin, Department of Theology and Religious Studies, Villanova University
See also the publisher’s page on this book.
From the back cover: ‘In this book, Stephen Cooper provides an overview of one of the greatest theologians of the early church: Augustine of Hippo. Through discussing the Confessions, Cooper introduces the life and thought of Augustine and examines his theological views that emerged through the important controversies of his time.’
Again from the back cover: ‘Stephen Cooper deftly takes us into Augustine’s complex ancient thought-world and surprises us with the discovery that his seemingly distant and foreign questions are still our own. With original and lively translations of the Confessions, we are made to feel the passion and provocation of Augustine’s own Latin prose. This is an integral work that conceals between the lines a wealth of contemporary scholarship on this pioneering Western theologian and the sweep of his spiritual vision.’ by Thomas F. Martin, Department of Theology and Religious Studies, Villanova University
See also the publisher’s page on this book.
S.A.クーパー『はじめてのアウグスティヌス』上村直樹訳 (東京: 教文館, 2012).
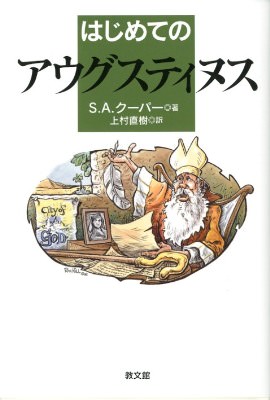
「アウグスティヌスの思想を、自伝文学の嚆矢ともされる主著『告白』(全十三巻)に従い、アームチェア・セオロジアン素人神学者向けのシリーズの一冊として手際よく説明する、すぐれた研究者による好著の邦訳である」(松崎一平『本のひろば』2012年6月号)と評されたこの翻訳には、原著にはない「日本語版への序文」をのせている。これは、翻訳出版が原著の刊行からおよそ10年後であるという事情から、原著刊行後この間にあらたに世に出た研究について読者に紹介されたいという訳者の希望にこたえて執筆されたエッセイである。新しい世紀にはいって最初の10年間の研究の動向について分かりやすく説明しているので、この翻訳の目次をあげたあとで、あらためて初稿段階の翻訳を紹介したい。実際に引用するにあたっては、出版された本自体を見てください。つぎに、訳者が日本語文献を中心に文献をつけくわえた「参考文献案内」(日本語文献を中心に、訳者編纂)もあわせて紹介する。これら二つの文章は、アウグスティヌスをいますこし学びたい人への案内になると思う。
- 日本語版への序文 3
- 謝辞 11
- はじめに──ともかく、アウグスティヌスとは誰のことなのか 17
- 第1章 ぼんやりとした始まり 33
- 第2章 愛にのぼせる若者 69
- 第3章 自立する青年 85
- 第4章 教師という職業 113
- 第5章 置いてきたこと 125
- 第6章 足踏み──苦しむ魂の世俗的な目標 145
- 第7章 光の上の光──プラトン主義者の書物との出会い 169
- 第8章 回心への転換 193
- 第9章 いくつもの死と新たな生活 221
- 第10章 はてしなき告白 243
- 第11章 司教という職責 265
- むすび 297
- 参考文献案内 309
- 訳者あとがき 319
- 索引 i
日本語版への序文
アウグスティヌスについて紹介する私の本が日本語へと翻訳されるにあたって、日本の読者に向けて語る機会を得たことを大変嬉しく思うとともに、上村直樹氏による慫慂に感謝したい。私の本が、他の言語へと人間の一言語に設けられている限界を越えるというこの展開は、ローマ帝国治下北アフリカの偉大な神学者の精神にすぐれて相応しい。というのは、その人にとって人類の多様性は、そのあり方の一体性を証言するものだったからだ [注1]。当然のことながら、ヒッポの司教の著作は特定の時と場所に結びついているのだが、この司教は、地上の国とその住人の多くの外観に備わる際立った特徴のすべてが「肉」の類いに分類され、それゆえ、人間の生の究極目的にとっては根本的でないという自分の主張を声高に語っている。その思想の内に認められる普遍的な見方──各々において具体的に示される人間本性が本質的には同一なのだから、個々に固有の文化を横断する対話が成立可能であり、また必要だ──によって、人間の条件や神の本性、キリストにおける生についてのアウグスティヌスの省察が、あらゆる人々や国や言葉、彼にじかに接した会衆が属した教会という領域の内と外その両方に関係すると認められてきたのはなぜなのか、その理由をたやすく説明することができるのである。
『はじめてのアウグスティヌス』は、『告白』本文が比類ない特徴を備え、アウグスティヌスの生涯と思想を明らかにしているために、この著作に専ら焦点を当てている。また、この本のなかで私は、アウグスティヌスのいくつもの浩瀚な著作のなかでも重要な問題について、『告白』が触れている多くの箇所に注目した。この「日本語訳への序文」において私は、およそ10年前にこの本が出版されて以降世に出たアウグスティヌスに関する学術的な多くの研究について指摘しておきたい。まず第一に、いまや英語圏の読者は、アウグスティヌスの著作について従来以上に数多くの新しい完全な翻訳を手に取ることができる。それらは、ニュー・シティー出版社から刊行中の叢書におさめられている [注2]。これ以外の最近の研究文献も、アウグスティヌスの生涯について、『告白』について、後期の多くの重要な著作について関心を抱いた読者がさらに深く分け入ってゆくに際して、私の本に足りないところを補うだろう。これらのなかでは、アウグスティヌスについての新しい包括的な概論 [注3]、アウグスティヌスの思想に関する論文集 [注4]、ジリアン・クラークによる新しい非常にすぐれた『告白』についての入門 [注5]、ウィリアム・マンが編集した『告白』についてのすばらしい論文集 [注6]を挙げることができる。非常に有益な研究書として、『告白』についての3巻本の註釈が、カール・ヴォートによって執筆された [注7]。『アウグスティヌスの『告白』読者必携』は、『告白』全13巻の各巻について有益な手引きとなる各章から構成されている [注8]。
現代の文学的な自伝という様式──もしくは、その見苦しい所産とも言える現代のメディアでの著名人たちの告白──に慣れ親しんでから『告白』に近づいてみる読者は、アウグスティヌスの自分自身についての語りがその当時どれほど新奇であったのか、もしかするとよく分からないかもしれない。私たちがそういうものだと知っているような自伝は、古代文学の独自のジャンルとして存在していなかったのだ [注9]。とはいえ、自伝的な要素は、古典古代とヘレニズム時代のさまざまな著述のうちに見出されるし、ギリシアの詩のうちにも時折自伝的な言及が散らばっている。また、政治家や文学上の人物も自分たちの政策、教説、あるいは生き方を明確に擁護するに当たって自伝的な語りを用いた。実質を伴う自伝的な話を収めている文学上最初の広範囲にわたっての断片は、紀元前4世紀の偉大な著作家たちのうちに見出される。弁論家デモステネスの『冠について(クテシポン擁護)』、教育者イソクラテスの『アンティドシス(財産交換)』、そしてもっとも有名なものとして、ソクラテスが自分の裁判で述べた弁明演説をプラトンが演出した『アポロギア』(プラトンの『第7書簡』もまた、この点から言及されるだろう)。紀元前1世紀までに、政治家の回顧録という文学様式が台頭してきた。もっとも有名なのは、キケロの書簡集である。1世紀になると、こうした自伝的な著述の傾向──ある論点を説明するため、ときに自分自身の生へ脱線する──は、セネカの書簡において一層哲学的な方向へ転回している。同様に、2世紀後半のローマ皇帝マルクス・アウレリウスの有名な『自省録』も一種の霊的な日記であるので、一層著しい内面への転回を伴う回顧録の様式を用いている。しかし、アウレリウスの書物『自省録』は、アウグスティヌスの『告白』が備えているような中心的な特徴を欠いているのだ。それは、自分の外にあるものに関する説明を霊的な深い次元での自己探索に結びつけようとする企てである。
「神の前の告白」という考えこそが、真にアウグスティヌスの諸著作を古代ギリシア・ローマの文学的な遺産から区別している。このモティーフは、聖書的ないくつかのモデルに照らして彼が展開したものだと理解されるべきだ。この点で、第一に重要なのは「詩篇」であり、魂の奥底からの神自身への呼び掛けのなかでもっとも痛切なものである。預言者たち──イザヤ、エレミア、エゼキエル、ホセア、アモス──のうちにも、また「伝道書」(コヘレトの言葉)の著者の黙想のうちにも認められる自伝的な要素と一緒に受け取ることで、この聖書的な文学、さらにその読解と共に生ずるキリスト教的な精神が、充全な霊的自伝である『告白』を著すことを可能にする地点までアウグスティヌスを到達させた契機だったのだろう。
こういった指摘は、私たちが古代以来所有している『告白』以外唯一である長編の自伝が、彼以外のキリスト教の司教ナジアンゾスのグレゴリオス [注10] の手に成るという事実が見出されることによって確認されることだろう。グレゴリオスの3篇の自伝的詩作は、聖職者としての経歴を閉じるころに書かれたのであり、アウグスティヌスが自分の生について書こうと着手するおよそ20年前だった。グレゴリオスがギリシア語で書いたからには、私たちは、アウグスティヌスに対して彼の詩作が直接に影響を与えたと認めることはほぼ不可能である。とはいえ、これら二人の自伝的な著作を一緒に取り上げることによってはっきりと示唆できるのは、ギリシアとラテンの文学様式が聖書的な伝統と結合したことが、自伝という文学ジャンルを生み出すに当たって決定的だったということだ。
アウグスティヌスについての自分の知識を『告白』の範囲を越えて拡げたいと望む読者は、アウグスティヌスのそれぞれ重要な著作に関する最近のモノグラフを見てみたいと思うだろう。とりわけ有益なのは、サイモン・ハリスンによる『自由意志論』についての徹底した分析であり [注11]、それに加え、アウグスティヌスの『三位一体論』に関しては、ルイージ・ジョイア [注12] とルイス・エアーズ [注13] による2冊の重要なモノグラフがある。アウグスティヌスの自由学芸への関与、また自由学芸を神学の課題へ適用する取り組みについて、近年多くの学問的な関心の中心になってきたのだが、その主題については、カルラ・ポルマンとマーク・ヴェッセイによって編集された論文集が充分な手引きになる [注14]。司牧する者としてのアウグスティヌスについて考察するすぐれた研究書が、ポール・コルベットによって最近公刊された [注15]。これは、古代哲学を霊的な教育学という特徴を著しく際立たせたものとして読み解くという傾向が強まっていることを充分に考慮している。アウグスティヌスの生涯について関心をかき立てるこれらの研究(その生涯についての諸相の多くは、彼の浩瀚な書簡と説教のうちに埋もれている)は、ジェームズ・オドンネルによるまったく異なる観点からの伝記とともに、いまやピーター・ブラウンの古典的な『アウグスティヌス伝』 [注16] を補うにたるものとなっている。このオドンネルによる聖人に対して批判的な伝記は、アウグスティヌスについて多くの労作を物してきたなかで最近の成果である [注17]。
解釈者たちを惹きつけ続けてきたのが『神の国』である。一方で、この著作が置かれていた元来の文脈において集中的に考察する研究があり [注18]、他方では、西洋の政治思想という見地からこの著作に取り掛かっている研究がある [注19]。ロバート・マーカスは、神の働きが聖書的な啓示の時代に続く世界の歴史のなかに紛れもなく明白に認めることはできないというアウグスティヌスの考えから導き出せる帰結として、神学者としてのアウグスティヌスが重要なのは世俗の社会的な領域に関する理解を切り開いたからだという自己の見解を、簡潔だがまことにすぐれた仕方で改めて提出している [注20]。
聖書解釈者としてのアウグスティヌスに関する研究もまた、同じように進展している [注21]。アウグスティヌスの比較的初期の『ガラティア書註解』──これはアウグスティヌスが聖書の一書について著したなかで唯一完全な註解──は、エリック・プルマーによる解説、分析を併せて翻訳され、プルマーは、パウロに関するラテン語で書かれた最初の註釈、マリウス・ウィクトリヌスの著作をおそらくはアウグスティヌスが読んだのではないかと議論している [注22]。パウロ書簡に関してそのつぎにラテン語での註釈を著した者──アンブロシアステルと呼ばれている匿名のローマ人の著者──にアウグスティヌスが依拠した痕跡は、1世紀以上もの間研究者によって注目されてきた [注23]。ポーラ・フレデリクセンの『アウグスティヌスとユダヤ人たち』は、アウグスティヌスがドナティスト派の神学者ティコニウスの解釈学の手引きに取り組むことで刺激を受け、パウロ神学についての理解を変化させている点について多くの論述を含んでいる [注24]。聖書解釈者としてのアウグスティヌスに興味を抱いた読者はまた、この主題について元々はフランス語で書かれた論文集に加えて [注25]、多くの論文がフランス語とドイツ語から翻訳されたすぐれた論文集も歓迎するだろう [注26]。
自らについていささかの苦悩を伴う黙想の結びにおいて、ある聖書記者は「多くの本を作ることには、かぎりがない。多くのものに熱中すると、身体が疲れる」(「伝道書」12:12、新改訂標準訳)ということに十分気づいていた。アウグスティヌスは、「伝道書」の結びの文が真実を含んでいることに反論しようとは考えないだろうが、一方では、自分の読者が、聖書やさらに自分自身の著述についてこのような類いの危惧を覚えることは求めないだろう。明らかに彼は、自分が『三位一体論』(8.3.4) で表明した心情と共に、自らの神学的な著作に取り組んでもらいたいと期待しているに違いない。「言説は甘美に教え、聞き手を適切に動かすときに善いものである」。私は、この言葉を添えて読者にこの私の小著を勧めたい。そしてこの小著によって、アウグスティヌス自身が多くの汗と多くのインキを要するにたると考えた事柄について、幾世紀をも超えた彼との対話が容易となることを望んでいる。私の書物の日本語訳がこの希望を満たすことによって、そして福音についてのアウグスティヌスの徹底した取り組みが海を越えて広がることによって、私は自身に与えられたこの機会に深く感謝したい。
注
- 『神の国』16.8.1 を参照。そこで彼は、古代の哲学的な考えに一致して、人間 (homo) を「理性を備えた可死的な動物」(animal rationale mortale) と定義する。それに続いて、「実際、人間がどこで生まれようとも、信仰ある者はだれもが、自分たちがあの一人の最初に作られた人間に起源を持つと断言するのをためらわない」と語っている。
- The Works of Saint Augustine: A Translation for the 21st Century (Hyde Park, NY: New City Press, 1991 on).
- Carol Harrison, Augustine: Christian Truth and Fractured Humanity (New York: Oxford University Press, 2000). さらに最近の文献として、William Harmless, Augustine in His Own Words (Washington, DC: Catholic University Press of America, 2010). ハームレスの著作は、近年発見されたアウグスティヌスの新書簡について考慮すると共に、その著作からの広汎にわたる申し分ない抜粋の集成である。
- Eleonore Stump and Norman Kretzmann (eds.), The Cambridge Companion to Augustine (Cambridge: Cambridge University Press, 2001). さらに、Roland Teske, To Know God and the Soul: Essays on the Thought of Saint Augustine (Washington: Catholic University of America, 2008)を参照。
- Gillian Clark, Augustine: The Confessions (Exeter: Bristol Phoenix Press, 2005).
- William E. Mann (ed.), Augustine’s Confessions: Critical Essays (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006).
- ニューヨーク州立大学出版局(オールバニー)から刊行され、その構成は、The Journey Toward God in Augustine’s Confessions: Books I–VI (2003); Encounters With God in Augustine’s Confessions: Books VII–IX (2007); Access to God in Augustine’s Confessions: Books X–XIII (2005).
- A Reader’s Companion to Augustine’s Confessions, edited by Kim Paffenroth and Robert Peter Kennedy (Lousville, KY: Westminster John Knox, 2003).
- この領域において最も信頼の置ける研究は、依然としてGeorg Misch, A History of Autobiography in Antiquity, 2 volumes (Cambridge: Harvard University Press, 1951; German original, 1907)である。
- この司教については、Brian E. Daley, Gregory of Nazianzus (Abingdon, UK: Routledge, 2006)を参照。
- Harrison, Simon, Augustine’s Way into the Will. The Theological and Philosophical Significance of De Libero Arbitrio (Oxford: Oxford University Press, 2006).
- Gioia, Luigi, The Theological Epistemology of Augustine’s De Trinitate (Oxford: Oxford University Press, 2008).
- Ayres, Lewis, Augustine and the Trinity (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
- Karla Pollmann and Mark Vessey (eds.), Augustine and the Disciplines: From Cassiciacum to Confesions (Oxford: Oxford University Press, 2007).
- Kolbet, Paul, Augustine and the Cure of Souls: Revising a Classical Ideal (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2010).
- Brown, Peter, Augustine of Hippo: A Biography については、カリフォルニア大学出版局から2000年に刊行された新たに資料を追加している第2版を参照〔この第2版からの日本語訳は、『アウグスティヌス伝』上・下、出村和彦訳(教文館、2004)〕。
- James J. O’Donnell, Augustine: A New Biography (New York: Harper Collins, 2005).
- Christian Tornau, Zwischen Rhetorik und Philosophie. Augustins Argumentationstechnik in De civitate Dei und ihr bildungsgeschichtlicher Hintergrund (Berlin: Walter de Gruyter, 2006).
- Miles Hollingworth, Pilgrim City: St Augustine of Hippo and his Innovation in Political Thought (London: T & T Clark, 2010). 政治哲学と理論という観点から著されたアウグスティヌスに関する研究文献に関して、このホリングワースの充実した文献表を参照のこと(特に注意すべきは、R・W・ダイソンの論文群である)。
- Robert Markus, Christianity and the Secular (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2006). この新しい著述において改めてその所見が示されているマーカス自身の重要な研究とは、Saeculum: History and Theology in St. Augustine (Cambridge: Cambridge University Press, 1989; 2nd ed)〔日本語訳は、『アウグスティヌス神学における歴史と社会』宮谷宣史・土井健司訳(教文館、1998)〕。
- アウグスティヌスのこの側面について概観するには、私の博士論文を指導してくださった先生による論考、Richard A. Norris, Jr., “Augustine and the Close of the Ancient Period of Interpretation” in Alan Hauser and Duane Watson (eds.), A History of Biblical Interpretation (vol.1): The Ancient Period (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2003)を参照のこと。フランス語を解する読者は、次の2篇の論考も参照すべきだろう。Martine Dulaey: “L’apprentissage de l’exégèse biblique par Augustin (1). Années 386–389”, Revue des Études Augustiniennes 48, 2002, pp. 267–295; “L’apprentissage de l’exégèse biblique par Augustin (2). Années 390–392”, Revue des Études Augustiniennes 49, 2003, pp. 43-84.〔これらの論文について、『中世哲学研究』京大中世哲学研究会、第22号 (2003) 126頁と第23号 (2004) 113頁に内容が紹介されている。〕 アウグスティヌスの後代への影響については、Michael C. McCarthy, “‘We Are Your Books’: Augustine, the Bible, and the Practice of Authority”, Journal of the American Academy of Religion, 75, 2007), pp. 324-352の最近の成果を参照。
- Eric Plumer, Augustine’s Commentary on Galatians: Introduction, Text, Translation, and Notes (Oxford: Oxford University Press, 2003). ウィクトリヌスによる「ガラティア書」註解については、Stephen A. Cooper, Marius Victorinus’ Commentary on Galatians (Oxford: Oxford University Press, 2005)を参照。
- この人物については、Sophie Lunn-Rockliffe, Ambrosiaster’s Political Theology (Oxford: Oxford University Press, 2007. より簡潔な紹介として、David Hunter, “The Significance of Ambrosiaster,” Journal of Early Christian Studies 17, 2009, 1–26を参照。
- Paula Fredriksen, Augustine and the Jews: A Christian Defense of Jews and Judaism (USA: Doubleday, 2008). ティコニウスの『諸規則の書』の校訂版と翻訳は、William S. Babcock, Tyconius: The Book of Rules (Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 1989).
- Augustine and the Bible, ed. Pamela Bright (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1999; French original, 1986).
- Augustine: Biblical Exegete, ed. Frederick Van Fleteren and Joseph C. Schnaubelt (New York: Peter Lang, 2001).
「参考文献案内」(日本語文献を中心に、訳者編纂)
著者クーパー教授が、最近の研究文献を「日本語訳への序文」において紹介しているので、ここでは日本語文献を中心に研究文献を追加しておきたい。I. アウグスティヌスの著作
アウグスティヌスの原典については、簡潔に「標準的な批評校訂版」が、また『告白』については、ジェームズ・オドンネルによる校訂テキストがあげられている。附言すれば、アウグスティヌスの全著作を網羅する批評校訂版全集はいまだ完結していないので、全集としては、17世紀に刊行された通称「マウリナ版」(あるいはそのリプリント版)がスタンダードである。- Sancti Aurelii Augustini opera omnia, opera et studio monachorum ordinis sanct Benedicti e congregatione s. Mauri, 11 volumes. Parisiis: Franciscus Muguet, 1679-1700.
- Sancti Aureli Augustini opera, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, editum consilio et impensis Academiae scientiarum austriacae. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1887 sqq.
- Sancti Aurelii Augustini opera, Corpus Christianorum, Series Latina. Turnhout: Brepols, 1954 sqq.
- Nuova Biblioteca Agostiniana, Opere di Sant’Agostino. Roma: Città Nuova Editrice, 1965 sqq.
- Augustine, Confessions, Book I-IV, ed. Gillian Clark, Cambridge Greek and Latin Classics: Imperial Library. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Augustine, The Confessions, trans. Philip Burton, with an introduction by Robin Lane Fox. London: Everyman’s Library, 2001.
- J. M. Quinn. A Companion to the Confessions of St. Augustine. New York: Peter Lang, 2003.
- 聖アウグスティヌス『告白』上・中・下、服部英次郎譯「岩波文庫」、岩波書店、1940・1949年。
- 『アウグスティヌス』、山田晶責任編集「世界の名著」第14巻、中央公論社、1968年。
- 岡野昌雄『アウグスティヌス『告白』の哲学』、創文社、1997年。
- 加藤信朗『アウグスティヌス『告白録』講義』、知泉書館、2006年。
- 『告白録』、宮谷宣史訳「アウグスティヌス著作集」第5巻、教文館、1993・2007年。
- 松崎一平『アウグスティヌス『告白』─〈わたし〉を語ること…』「書物誕生─あたらしい古典入門」、岩波書店、2009年。
- 『アウグスティヌス著作集』全30巻、教文館、1979年-。
- アウグスチヌス『ソリロキア・浄福の生』、高桑純夫譯、筑摩書房、1949年。
- アウグスチヌス『秩序論』、高橋亘譯、中央出版社、1954年。
- アウグスチヌス『カトリック教会の道徳』、熊谷賢二訳「キリスト教古典叢書」2、創文社、1963年。
- アウグスチヌス『教えの手ほどき』、熊谷賢二訳「キリスト教古典叢書」4、創文社、1964年。
- 『アウグスティヌス ボエティウス』、渡辺義雄訳「世界古典文学全集」第26巻、筑摩書房、1966年(『告白』、『幸福な生活』、『独白』所収)。
- アウグスティヌス『主の山上のことば』、熊谷賢二訳「キリスト教古典叢書」8、創文社、1970年。
- 『アウグスティヌス 教師論』、石井次郎・三上茂訳「世界教育学選集」98、明治図書出版、1981年。
- アウグスティヌス『ヨハネ福音書講解』上・下、中沢宣夫訳、新教出版社、1996-1997年。
- 岡部由紀子『アウグスティヌスの懐疑論批判』、創文社、1999年。
II. アウグスティヌスの生涯
アウグスティヌスの生涯や、その歴史的な背景を考えるうえで、最初にあげる『初期ラテン教父』は、アウグスティヌスと関わりの深い古代キリスト教思想家に関する翻訳と解説の集成である。セルジュ・ランセルによるアウグスティヌスの伝記は、邦訳が出版されたピーター・ブラウンの『アウグスティヌス伝』以降の研究成果を踏まえ、ブラウンがあまり言及することのなかったアウグスティヌスの神学について考察するとともに、あらたに発見された説教や書簡についても検討を加えている。- 『初期ラテン教父』、上智大学中世思想研究所・加藤信朗編訳監修「中世思想原典集成」第4巻、平凡社、1999年。
- A・アマン『アウグスティヌス時代の日常生活』上・下、東丸恭子・印出忠夫訳、リトン、2001-2002年。
- Serge Lancel. St Augustine, trans. Antonia Nevill. London: SCM Press, 2002.
- ピーター・ブラウン『アウグスティヌス伝』上・下、出村和彦訳、教文館、2004年。
- 長谷川宜之『ローマ帝国とアウグスティヌス─古代末期北アフリカ社会の司教』、東北大学出版会、2009年。
III. アウグスティヌス研究
まず、「日本語訳への序文」において紹介された研究文献に、以下の著作も追加しておきたい。- Augustine: On Christian Teaching, trans. R. P. H. Green, Oxford World’s Classics. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Gerald O’Daly. Augustine City of God: A Reader’s Guide. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Donald X. Burt. Friendship & Society: An Introduction to Augustine’s Practical Philosophy. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999.
- Phillip Cary. Augustine’s Invention of the Inner Self: The Legacy of a Christian Platonist. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Carol Harrison. Rethinking Augustine’s Early Theology: An Argument for Continuity. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Philip Burton. Language in the Confessions of Augustine. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Roland J. Teske. Augustine of Hippo: Philosopher, Exegete, and Theologian. A Second Collection of Essays. Milwaukee: Marquette University Press, 2009.
- Henry Chadwick. Augustine of Hippo: A Life, with foreword by Peter Brown. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Edward Morgan. The Incarnation of the World: The Theology of Language of Augustine of Hippo. London: T & T Clark, 2010.
- 宮谷宣史『アウグスティヌス』、「人類の知的遺産」15、講談社、1981年(「講談社学術文庫」、2004年)。
- 『アウグスティヌスを学ぶ人のために』、金子晴勇編、世界思想社、1993年。
- Hubertus R. Drobner. Fathers of the Church: A Comprehensive Introduction, trans. Siegfried S. Schatzmann; with bibliographies updated and expanded for the English edition by W. Harmless and H. R. Drobner. Peabody, Mass.: Hendrickson, 2007.
- 『神との対話─中世・信仰と知の調和─』、中川純男責任編集「哲学の歴史」第3巻、中央公論新社、2008年。
- 山田晶『アウグスティヌスの根本問題─中世哲学研究第一』、創文社、1977年。
- 山田晶『アウグスティヌス講話』、新地書房、1986年(「講談社学術文庫」、1995年)。
- R・A・マーカス『アウグスティヌス神学における歴史と社会』、宮谷宣史・土井健司訳、教文館、1998年。
- 中川純男『存在と知 アウグスティヌス研究』、創文社、2000年。
- ギャリー・ウィルズ『アウグスティヌス』、志渡岡理恵訳「ペンギン評伝双書」、岩波書店、2002年。
- 富松保文『アウグスティヌス─〈私〉のはじまり』、シリーズ「哲学のエッセンス」、日本放送出版協会、2003年。
- H・I・マルー『アウグスティヌスと古代教養の終焉』、岩村清太訳、知泉書館、2008年。
